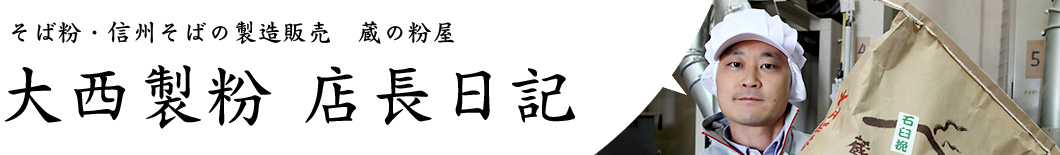幻の在来種「牡丹そば」とは ― 北海道ピンネ農協が守り続ける伝統の味
2025年9月18日

牡丹そば圃場
牡丹そばのはじまり
「牡丹そば」は、
1930年に北海道伊達町の農家が
在来そばから選び抜いた系統です。
道立農事試験場(現在の北海道立総合研究機構=道総研)が
奨励品種として広め、
その豊かな香りと甘みで高い評価を得ました。
しかし、
国の登録品種のように
一元的な管理が行われていたわけではありません。
各地の農家が自家採種を繰り返すことで受け継がれ、
その過程で
「富良野系」「上川系」といった
地域ごとの個性が生まれました。
いま私たちが手にする牡丹そばは、
土地の歴史と農家の努力が刻まれた
“生きた在来種”なのです。
なぜ“幻のそば”と呼ばれるのか
1970~80年代、
北海道で栽培されていたソバの過半は
牡丹そば系統でした。
つまり、
かつて北海道の畑の多くを覆っていたのが
牡丹そばだったのです。
しかし1989年に登場した改良品種
「キタワセソバ」に主役の座を譲り、
牡丹そばの作付けは急速に減少。
加えて栽培の難しさや収量の低さから
市場に出回ることも少なくなり、
やがて「幻のそば」と呼ばれる存在になりました。
JAピンネによる原々種の継承
浦臼町・新十津川町の
JAピンネ(ピンネ農協)は、
この希少なそばを未来に残すため、
原々種(もっとも純粋な種)を厳重に管理し、
地域ぐるみでブランド化に取り組んでいます。
2009年には
神内ファームの設立した財団と覚書を交わし、
種子管理から栽培・販売までを一体的に行う仕組みを確立しました。
現在は
約540haで220トンを生産し、
日本で最も安定して牡丹そばを供給できる拠点となっています。
牡丹そばが「本物」として信頼されるのは、
JAピンネが原々種を守っているからこそなのです。
幻から現実へ ― 大西製粉が届ける牡丹そば粉
この希少な牡丹そば粉が、
今年から大西製粉に届くことになりました。
信州小諸の石臼でゆっくりと挽き上げることで、
牡丹そばが本来持つ香りと甘みを最大限に引き出します。
そば打ち愛好家が手にすると、
生地のしまりが良く、立ちのぼる香りが格別。
まさに
“幻の在来種”にふさわしいそば打ちとなるでしょう。
伝統をつなぐ一鉢
1930年の選抜から90余年。
研究者の知恵、農家の粘り強い継承、
JAピンネの現代的な管理、
そして製粉の技術。
すべてが重なり合い、一つの鉢の中に結晶します。
あなたが打つ牡丹そばは、
北海道の大地から信州の石臼を経て、
食卓へと続く物語の証なのです。
よくある質問(Q&A)
Q1. 牡丹そばとは?
A. 牡丹そばは、1930年に北海道伊達町の農家が在来そばから選抜した系統で、香りと甘みが強いのが特徴です。道立農事試験場(現在の道総研)が奨励品種として広めましたが、全国的に流通することは少なく、北海道の一部地域に根付いてきました。現在はJAピンネが原々種を守り、浦臼町・新十津川町を中心に栽培が続けられています。
Q2. なぜ「幻のそば」と呼ばれるのですか?
A. 牡丹そばは栽培が難しく、収穫量が限られているため、市場に出回ることがほとんどありませんでした。その希少性と独特の風味から「幻のそば」と呼ばれるようになったのです。近年はJAピンネの管理により、ある程度まとまった量が安定供給されていますが、それでも限られた製粉所や飲食店でしか味わえません。
Q3. 牡丹そばの特徴は?
A. 大粒で香りが高く、甘みがあり、粉にするとコシのあるそばに仕上がります。粗挽きで挽くと香りが際立ち、立ちのぼる甘い香りが楽しめます。生地はしまりが良く、そば打ち愛好家にとって扱いやすいのも魅力です。
Q4. どこで食べられますか?
A. 北海道浦臼町の「そば処ぼたん亭」など、産地周辺のお店で味わえるほか、JAピンネを通じて流通した粉を扱う製粉所や専門店で入手できます。大西製粉でも今年から牡丹そば粉の取り扱いを始め、家庭でのそば打ちに利用できるようになりました。
Q5. 牡丹そばと他の品種の関係は?
A. 北海道の主力品種「キタワセソバ(1989年育成)」は、牡丹そば(富良野系)をルーツに持つ選抜系統です。つまり、現代の標準的なそばの血筋にも牡丹そばの系統が受け継がれています。